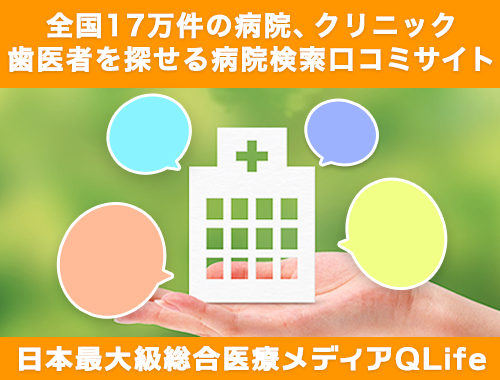高山病になりやすい場所・人がいる?どんな症状が出てくるの?
2020/7/25

山登りをしたとき、高所に体がうまく適応できずさまざまな体調不良を起こす高山病。誰にでも起こり得る症状ですが、発症しやすい場所・人があることをご存知でしょうか。今回は高山病になりやすい場所・人の条件について、高山病の症状と予防法と一緒に、確認していきましょう。
高山病とは
高山病は、高い山に登ったときに発生するさまざまな体調不良の総称です。平地に比べ、山頂の方が気圧が低く体に取り込める酸素が少ないために起こる症状ですが、なかには低い標高の山登りで重症の症状を表す方もいます。高山病は標高に関係なく、山登りをする方なら誰もが発症する可能性がある症状です。
高山病になりやすい場所は?
高山病は、標高が2000m以上になると発症リスクが上がることがわかっています。たとえば以下のような山・地点は、高山病になりやすい場所の条件を満たしていると言えます。
- 富士山
- 山頂の標高が3776mの富士山は、標高2300mを超える5合目のあたりから、高山病になりやすい環境条件を満たしています。
- エベレスト
- 世界最高峰、標高8848mのエベレストももちろん高山病になりやすい場所の条件を満たしています。なお標高8000m以上は、酸素ボンベがないと長時間滞在ができません。
- ペルーのアンデス山脈にある観光拠点:クスコとマチュピチュ
- クスコは標高3400m、マチュピチュは標高2400m地点のアンデス山脈にあります。
世界遺産に登録されているインカ帝国の遺跡・マチュピチュは世界的に有名な観光地で、クスコはマチュピチュに向かうための、玄関口となる観光拠点の町です。どちらも標高2000m以上で、かつ、観光のために平地から急激に高度を上げてくる方も多いため、高山病に非常になりやすい場所です。
高山病になりやすい人は?
誰にでも発症する可能性がある高山病ですが、基本的には加齢とともに肺活量が減少し、動脈硬化が進んでいる高齢者の方が、発病リスクが高いと言われています。
そのほか、高山病を起こしやすい方の条件として以下のようなものがあります。
- 家族または親族に、登山したときに高山病にかかった経験を持つ人がいる
- 前日、または当日にアルコールを摂取している
- 登山する当日、出発前から体調不良があった
- 脱水症状を起こしている
高山病になると出てくる症状は?
高山病の症状は、大きく「山酔い」「高所肺水腫」「高所脳浮腫」の3つに分けられます。
山酔い
高山病の初期段階、最も軽い症状です。二日酔いに近い症状だと言われています。具体的には頭痛に加え食欲低下、吐き気・嘔吐などの消化器症状、全身の倦怠感や脱力感、立ち眩み、めまい、不眠、息苦しさなどの症状を1つ以上併発します。
高所肺水腫
低酸素状態が原因で、肺の血管から水分が染み出してくる症状です。安静時の呼吸困難や咳、胸の圧迫感、頻脈、歩行困難などの症状を伴います。発症には遺伝的要因も強く、山酔いと併発することが多いですが、数時間で急速に悪化することもあるので注意が必要です。
高所脳浮腫
低酸素状態が原因で、脳の血管から水がしみ出してくる症状です。山酔いに加え、まっすぐ歩けない運動失調や、日時や現在地がわからなくなる見当識障害が見られるようになる重篤な症状です。速やかに下山して適切な治療を受けなければ、昏睡状態に陥りやがて死亡します。
高山病を予防するために
高山病による体調不良や、命の危険を予防するには、登山の前や最中に以下のポイントに気を付けておくのが効果的です。
多めに水分を摂取して、脱水症状を防ぐ
体に負担がかかる登山中には、汗や呼吸から気づかない間に体の水分が失われ、脱水症状に陥ることも少なくありません。脱水症状からの高山病発症を防ぐためにも、のどが渇いたと感じる前に、10分に1回を目安にこまめに水分補給をしましょう。
体の状態に合わせて、無理をせずゆっくり登る
平地に比べ酸素を取り込むのが難しい高所では、無理をして動くと余計に酸欠状態になり、高山病を起こしやすくなります。自分のペースでゆっくり体を動かしながら高度を上げていけば、体が順応する時間の余裕が生まれ高山病を起こしにくくなります。
登山の前日と当日は、アルコールの摂取を控える
アルコールは脱水を促進し、高山病の発症と悪化を招きます。登山の前日からアルコールの摂取を控えて、体調を整えるようにしてください。
おわりに:標高2000m以上、高齢者や体調不良の人は高山病になりやすい
高山病は、高所の低気圧・低酸素状態に体が適応できずに、山酔いや高所肺水腫、高所脳浮腫などの症状を起こす疾患です。山酔いでは頭痛や吐き気、倦怠感や睡眠障害など二日酔いのような症状のみですが、より重症な肺水腫・脳浮腫になると命を落とすリスクもあります。標高2000m以上の高地の条件下で、高齢者や体調不良があった人が特に発症しやすいとされますので、登山をするときは無理をせず体調を整えて高山病を予防しましょう。